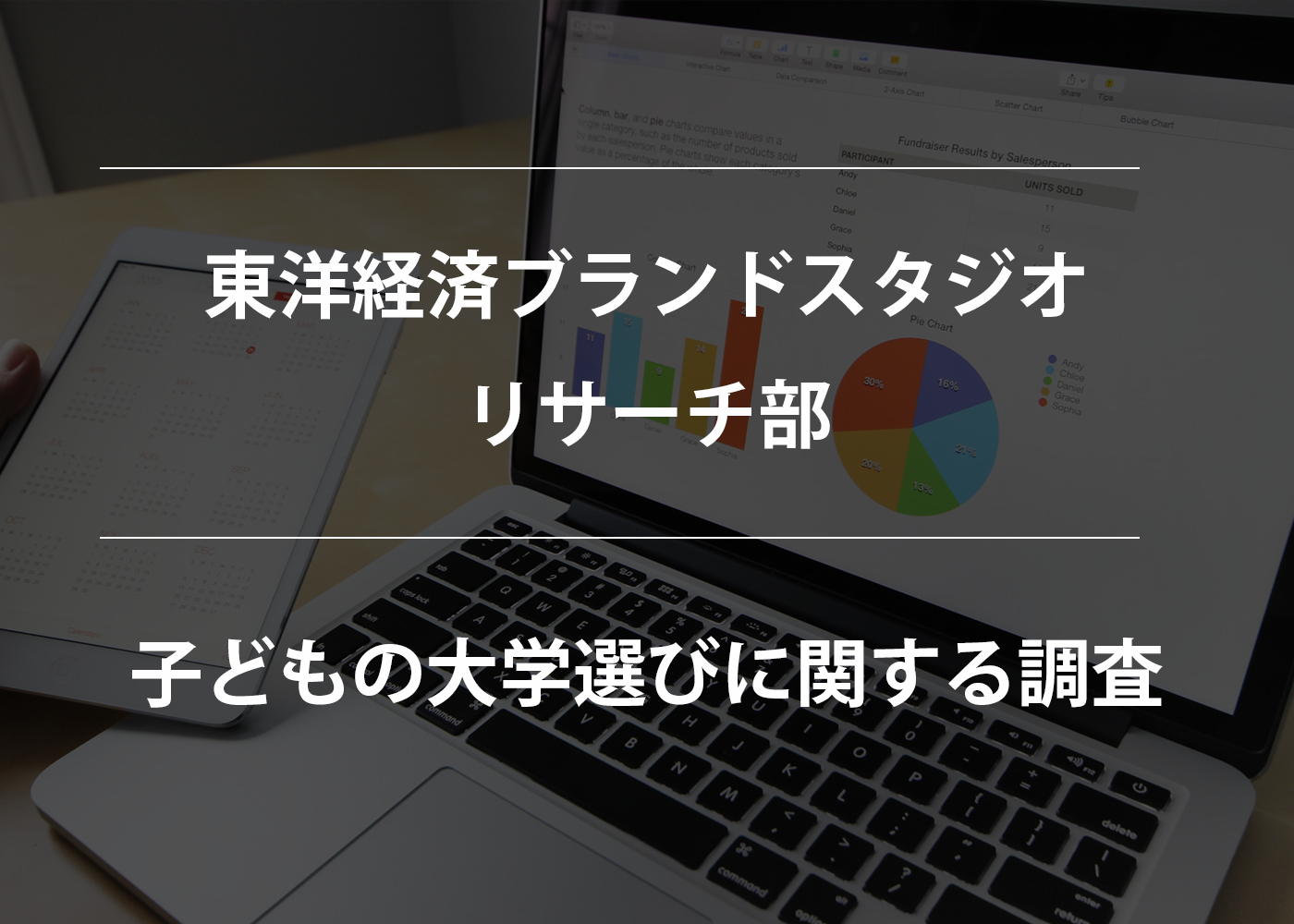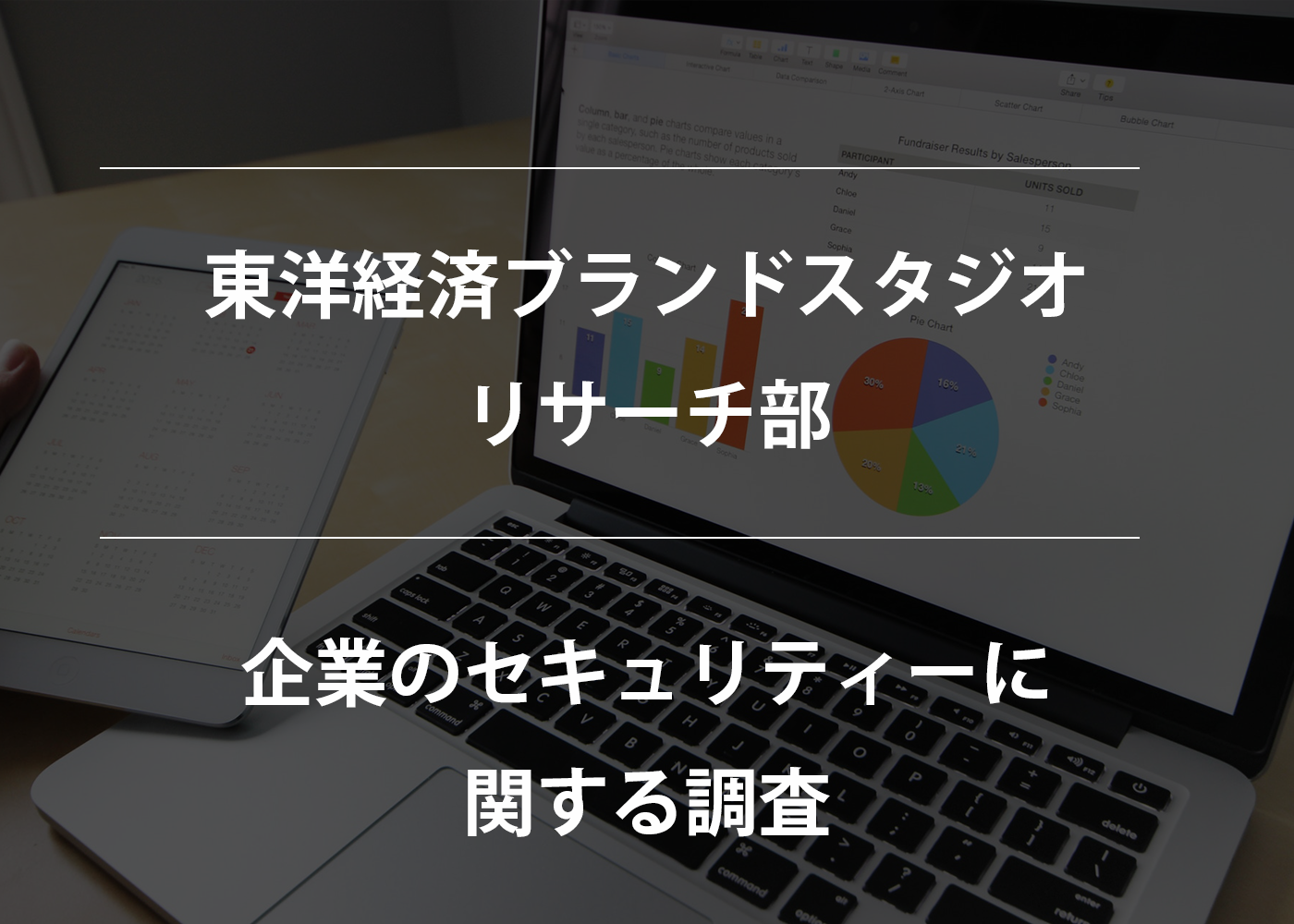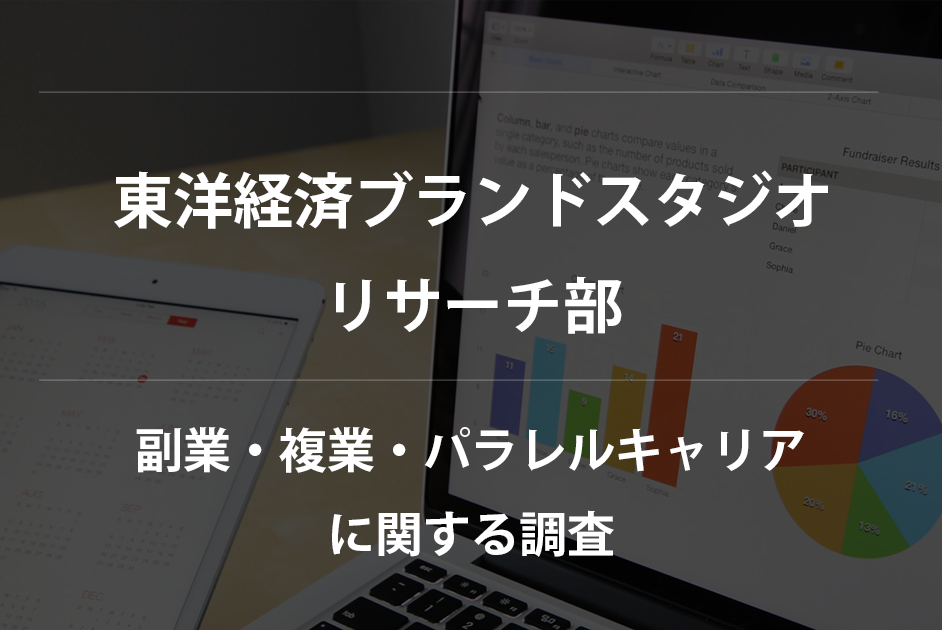東洋経済新報社ビジネスプロモーション局カスタム事業部では、お客様が情報を発信する際のコンテンツ制作をトータルで支援しています。
今回は、長年ビジネス書の編集者として書籍や雑誌の編集に携わってきたビジネスプロモーション局カスタム事業部長の齋藤宏軌に、小社のオウンドメディア、広報誌制作支援サービスの特長について聞きました。
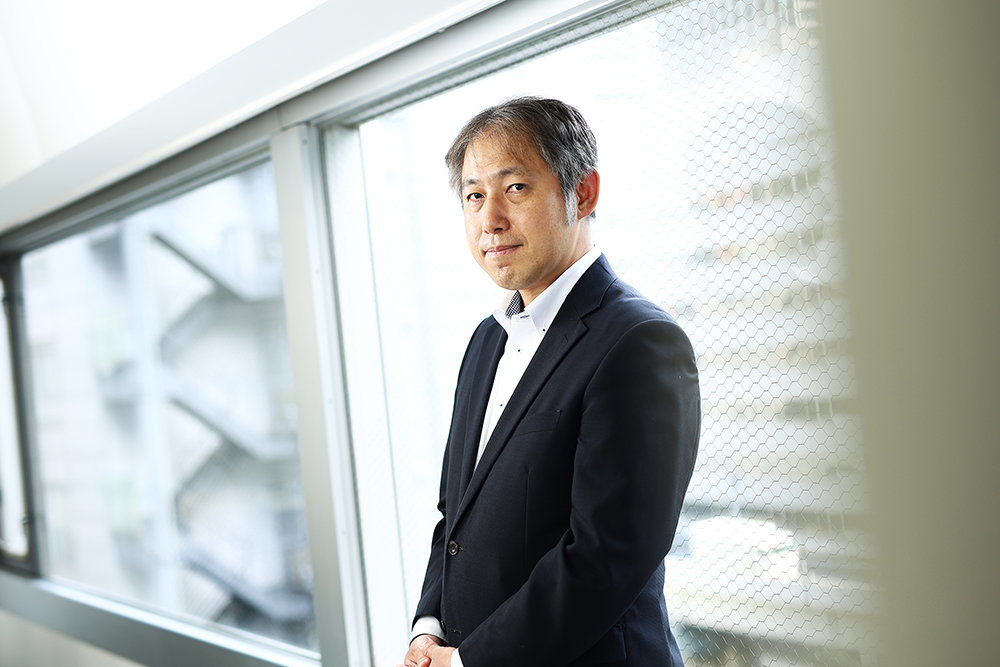
ビジネスプロモーション局カスタム事業部 部長 齋藤宏軌
今回は、長年ビジネス書の編集者として書籍や雑誌の編集に携わってきたビジネスプロモーション局カスタム事業部長の齋藤宏軌に、小社のオウンドメディア、広報誌制作支援サービスの特長について聞きました。
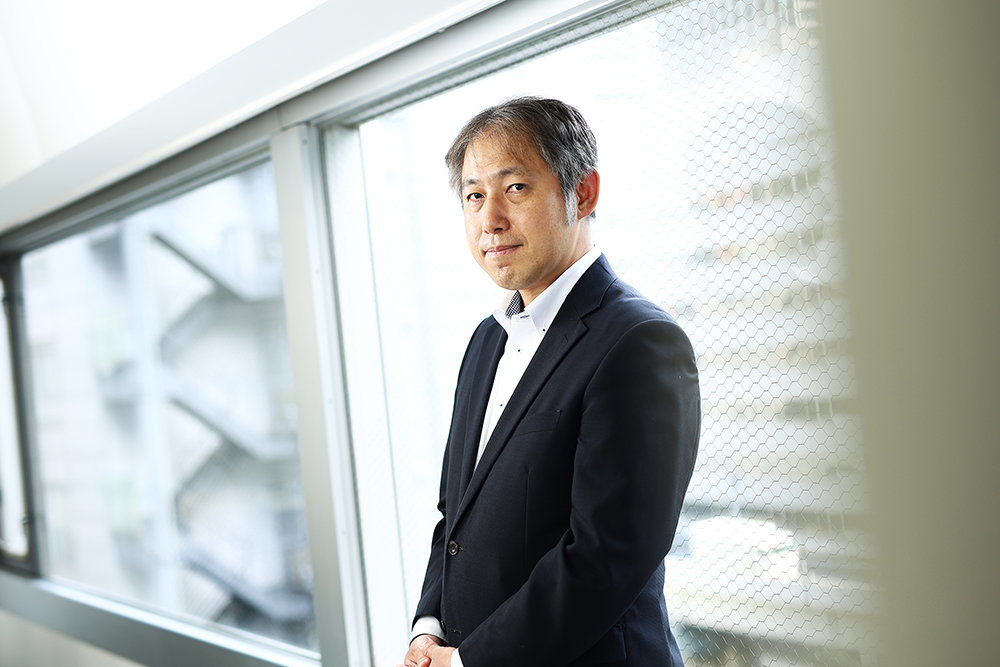
ビジネスプロモーション局カスタム事業部 部長 齋藤宏軌
――自己紹介をお願いします。
ビジネスプロモーション局カスタム事業部長の齋藤宏軌です。私は長年、ビジネス書の書籍編集者としてキャリアを積んでまいりました。前職は他の出版社で約8年間、自己啓発書を中心に約40冊の本を手がけました。
34歳で東洋経済新報社に転職し、出版局で前職と同じくビジネス書の編集に携わってきました。とくに多く手がけたのが、コンサルティングファームや金融機関、大手メーカーの経営者の方々の書籍です。代表作は『外資系コンサルのスライド作成術』『外資系コンサルのプレゼンテーション術』などの「外資系コンサルシリーズ」です。好評につき、10年以上のロングセラーとなっています。
ムックや季刊誌の編集も経験しました。『Think!』(2015年秋号をもって休刊)という雑誌の3代目の編集長も務めさせていただきました。これまでの累計だと、150冊以上の書籍やムックを制作してきたことになります。
2024年7月からは、ビジネスプロモーション局カスタム事業部の部長として、約20名の部員を率いています。
――売れる企画や著者の選定において、どのようなお考えがありましたか?
時代によって考え方は変化してきました。2000年代ごろまでは、米国で流行した新しい経営のキーワードやMBA関連の概念がコンサルティングファーム経由で日本に輸入され、それが書籍として売れる時代でした。
しかし10年代以降は、そうしたコンサルティングファームのブランド力や新しい経営コンセプトだけで売れる時代は終わりました。代わりに、コンサルティングファーム出身者が、自身の経験を具体的な仕事スキルやハウツーに落とし込んで教える書籍が求められるようになりました。
現在では、必ずしも有名コンサルティングファーム経験者でなくても、あるいは在籍期間が短くても、個人の発信力があり、ビジネスパーソンが「これを使えば役立つ」と感じる具体的なノウハウを提供できる方が重宝される傾向があります。この傾向も、数年経つとまた変わっていくのでしょう。

――現在部長を務められているカスタム事業部について、簡単にご説明いただけますでしょうか。
東洋経済新報社は、『週刊東洋経済』『会社四季報』「東洋経済オンライン」、そして私が携わってきた書籍など、多様な媒体を発行しています。カスタム事業部では、これらの媒体で培ってきたノウハウを生かし、企業の皆様の情報発信、PR、ブランディングをお手伝いしています。
具体的な手段としては、書籍、雑誌、小冊子、ムックといった紙媒体から、最近ではオウンドメディアや統合報告書の作成まで、多岐にわたります。これらのメディアをパッケージングし、流通させたり、特定のターゲットに届けたりすることで、企業の情報発信力向上やブランド構築に貢献しています。
――今回はその中でとくにオウンドメディアと広報誌についてお聞きしたいと思います。小社のオウンドメディアと広報誌制作支援について、特長を教えてください。
小社のオウンドメディアと広報誌には、主に3つの強みがあります。
1つ目は「多様な人材による専門性の高さ」です。
カスタム事業部には、約20名の部員が在籍しており、それぞれが異なるメディアのプロフェッショナルです。商業出版の雑誌編集長経験者、私のような書籍編集者、ウェブメディアの経験者など、多様なバックグラウンドを持つ人材がそろっています。お客様からのどのようなオーダーに対しても、適切なチームを編成し、対応することができます。また、メディアの種類だけでなく、アカデミック、金融、経済、経営といったジャンルにおいても、それぞれに強い専門性を持つメンバーがいますので、お客様のニーズに合わせて柔軟に対応できるのが強みです。
2つ目は「 他部署との連携による豊富なネットワーク」です。
広報誌やオウンドメディアの制作において、有識者へのインタビューや対談企画は欠かせません。カスタム事業部内でも候補者の選定は行いますが、必要に応じて『週刊東洋経済』『会社四季報』の記者、出版局の編集者といった他部署の専門家と連携します。彼らは各業界の第一人者とのコネクションを多く持っており、アポイントメントの成功率も非常に高いからです。
最近では、編集局の記者による勉強会も定期的に開催しており、カスタム事業部のメンバーもつねに最新の知見をインプットしています。これにより、お客様に対して、よりフレッシュで質の高い企画アイデアを提案できるよう努めています。
3つ目は「経済・ビジネス系メディアとしての深い知見」です。
私たちは長年、ビジネス系の雑誌や書籍を制作してきた経験から、法人のお客様、とくに経営者の方々が何を考え、どのような課題を抱えているかを深く理解しています。オウンドメディアや広報誌を制作する際には、まず企業の経営者が「何を目的とし、誰にリーチしたいのか」を最も重視します。単に面白いコンテンツを提供するだけでなく、読者が「これは自分にとって必要だ」と感じ、企業のメッセージが的確に伝わるようなコンテンツ作りを心がけています。単に多くの人に読まれることを目指すエンタメ系メディアとは異なる、ビジネスに特化したわれわれならではの強みだと自負しています。
――どのようなお客様のニーズに対して企画を提案されてきたのでしょうか。
広報誌では、金融機関、シンクタンク、メーカー、不動産企業など、幅広い業種のお客様とお取引させていただいています。
ある金融機関の会報誌では、「会員の維持」という課題がありました。そこで私たちは、会員である中小企業の経営者の方々が「この会に入っている意味がある」と感じられる内容を企画しました。具体的には、企業の法務・税務に関する最新情報を毎回アップデートできるコーナーや、会員企業の社長を丹念に取材しその奮闘ぶりを紹介する企画です。これにより、読者である経営者の方々が「自分と同じ会員がこんなに頑張っている」「このコミュニティーに属していることに誇りを感じる」といった帰属意識を高めることに成功しました。実際に、会員向けの勉強会では「読み応えがある」「毎号勉強になる」といった高い評価をいただいています。
オウンドメディアでは、メーカー、シンクタンク、リース企業、不動産会社などのお客様の支援をさせていただいております。小社の強みの1つは、「東洋経済オンライン」との連携です。あるお客様は、専門性の高い内容を発信したいというご要望をお持ちでしたが、専門性が高まるほど読まれにくくなるという課題がありました。そこで、「東洋経済オンライン」に記事を転載することで、より多くの読者にリーチし、閲覧数を増やすことができました。
別のお客様からは、「以前は自社で取材のアポイントを取ろうとしても、成功率が極めて低かったが、東洋経済と組んでからは高い確率でアポイントが取れるようになった」というお声をいただきました。東洋経済のブランドと実績が、取材先からの信頼につながっている証拠だと感じています。

――齋藤さんが考える「よいコンテンツ」とは何でしょうか?
私は「コンテンツはプレゼント」だと考えています。プレゼント選びが上手な人と下手な人がいますよね。コンテンツ作りも同じだと思っています。
よいコンテンツとは、「もらった人がどう喜ぶか、何をもらったら喜ぶか」を徹底的に考えて作られたものです。相手が喜んでくれれば、自然と贈った側もハッピーになれます。
私も過去には、「これは皆が読むべきだ」という独善的な思いで本を作ってしまい、全然売れなかったという経験があります。「求めていないもの」をプレゼントしても駄目なのです。
選ぶのに困って、安直に高価な品やブランド品、流行の品を選びたくなってしまいます。そういった品でも喜んでもらえる場合もあるかもしれませんが、そうではなく、徹底的に考えた結果、「本当に喜んでもらえる品」を考えて見つけ出すのがプロだろうと思います。
ときには、受け取り手自身が「本当のニーズ」に気づいていないこともあります。編集者やコンテンツ制作者は、読者やお客様が本当は何を望んでいるかを見つけ出す努力をして、そこをうまく捉えたコンテンツが、最高のプレゼントになるのです。
――今後、カスタム事業部で実現していきたいことは何でしょうか?
今後、カスタム事業部で注力していきたいのは、「テクノロジーの導入」です。
現在、広報物、冊子、書籍、オウンドメディアといった制作物は、アナログな手法で作られています。しかし、情報発信の未来を考えると、新たなテクノロジーの活用は不可欠です。
例えば、この10年で動画メディアは急速に成長しました。かつては何か困ったことがあれば本を読むのが当たり前でしたが、今はYouTubeで情報を得るのが一般的です。企業のブランディングや情報発信を考えるうえで、動画制作は避けて通れない領域だと認識しており、今後は積極的に取り組んでいきたいと考えています。
また、生成AIも大きな可能性を秘めています。
AIを活用することで、制作にかかる工数やコストを削減できます。これまで費用面で企業出版・カスタム出版に手が届かなかった企業様にも、AIを活用したエコノミーパッケージのような形でサービスを提供できるようになるかもしれません。制作期間の短縮も期待でき、これまで支援しきれなかった領域にも対応できるようになるでしょう。
テクノロジーを導入することで、より多くの企業様を支援できる体制を構築していきたいと考えています。
――最後に、クライアントの皆様へメッセージをお願いします。
私は30年近くビジネス書業界に身を置いていますが、この業界では昔から「よいものを作れば売れる時代は終わった」という一文が頻繁に使われてきました。これは、企業の皆様も痛感されていることと思います。今は、よい製品やサービスを作るだけでなく、それをいかに伝え、自社の商品やサービスがお客様にとってどのような価値を持つのかを発信していくことが、企業として生き残るために不可欠な時代です。
企業が税金で困れば税理士に、法律で困れば弁護士に相談するように、情報発信で悩んだ際には、情報発信の専門家にご相談いただくのが最善だと考えます。
とくに日本企業の大多数を占める中小企業の方は、大手広告代理店と継続的に付き合うことはコストの面で、すべてを自社で実施するのはリソースの面で、それぞれ現実的ではないと思います。
そのようなときにこそ、ぜひ一度、東洋経済新報社のカスタム事業部のサービスを思い出していただければ幸いです。
私たちは、長年の経験と専門知識、そして多様な人材とネットワークを生かし、貴社の情報発信を強力にサポートさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。
ビジネスプロモーション局カスタム事業部長の齋藤宏軌です。私は長年、ビジネス書の書籍編集者としてキャリアを積んでまいりました。前職は他の出版社で約8年間、自己啓発書を中心に約40冊の本を手がけました。
34歳で東洋経済新報社に転職し、出版局で前職と同じくビジネス書の編集に携わってきました。とくに多く手がけたのが、コンサルティングファームや金融機関、大手メーカーの経営者の方々の書籍です。代表作は『外資系コンサルのスライド作成術』『外資系コンサルのプレゼンテーション術』などの「外資系コンサルシリーズ」です。好評につき、10年以上のロングセラーとなっています。
ムックや季刊誌の編集も経験しました。『Think!』(2015年秋号をもって休刊)という雑誌の3代目の編集長も務めさせていただきました。これまでの累計だと、150冊以上の書籍やムックを制作してきたことになります。
2024年7月からは、ビジネスプロモーション局カスタム事業部の部長として、約20名の部員を率いています。
――売れる企画や著者の選定において、どのようなお考えがありましたか?
時代によって考え方は変化してきました。2000年代ごろまでは、米国で流行した新しい経営のキーワードやMBA関連の概念がコンサルティングファーム経由で日本に輸入され、それが書籍として売れる時代でした。
しかし10年代以降は、そうしたコンサルティングファームのブランド力や新しい経営コンセプトだけで売れる時代は終わりました。代わりに、コンサルティングファーム出身者が、自身の経験を具体的な仕事スキルやハウツーに落とし込んで教える書籍が求められるようになりました。
現在では、必ずしも有名コンサルティングファーム経験者でなくても、あるいは在籍期間が短くても、個人の発信力があり、ビジネスパーソンが「これを使えば役立つ」と感じる具体的なノウハウを提供できる方が重宝される傾向があります。この傾向も、数年経つとまた変わっていくのでしょう。

――現在部長を務められているカスタム事業部について、簡単にご説明いただけますでしょうか。
東洋経済新報社は、『週刊東洋経済』『会社四季報』「東洋経済オンライン」、そして私が携わってきた書籍など、多様な媒体を発行しています。カスタム事業部では、これらの媒体で培ってきたノウハウを生かし、企業の皆様の情報発信、PR、ブランディングをお手伝いしています。
具体的な手段としては、書籍、雑誌、小冊子、ムックといった紙媒体から、最近ではオウンドメディアや統合報告書の作成まで、多岐にわたります。これらのメディアをパッケージングし、流通させたり、特定のターゲットに届けたりすることで、企業の情報発信力向上やブランド構築に貢献しています。
――今回はその中でとくにオウンドメディアと広報誌についてお聞きしたいと思います。小社のオウンドメディアと広報誌制作支援について、特長を教えてください。
小社のオウンドメディアと広報誌には、主に3つの強みがあります。
1つ目は「多様な人材による専門性の高さ」です。
カスタム事業部には、約20名の部員が在籍しており、それぞれが異なるメディアのプロフェッショナルです。商業出版の雑誌編集長経験者、私のような書籍編集者、ウェブメディアの経験者など、多様なバックグラウンドを持つ人材がそろっています。お客様からのどのようなオーダーに対しても、適切なチームを編成し、対応することができます。また、メディアの種類だけでなく、アカデミック、金融、経済、経営といったジャンルにおいても、それぞれに強い専門性を持つメンバーがいますので、お客様のニーズに合わせて柔軟に対応できるのが強みです。
2つ目は「 他部署との連携による豊富なネットワーク」です。
広報誌やオウンドメディアの制作において、有識者へのインタビューや対談企画は欠かせません。カスタム事業部内でも候補者の選定は行いますが、必要に応じて『週刊東洋経済』『会社四季報』の記者、出版局の編集者といった他部署の専門家と連携します。彼らは各業界の第一人者とのコネクションを多く持っており、アポイントメントの成功率も非常に高いからです。
最近では、編集局の記者による勉強会も定期的に開催しており、カスタム事業部のメンバーもつねに最新の知見をインプットしています。これにより、お客様に対して、よりフレッシュで質の高い企画アイデアを提案できるよう努めています。
3つ目は「経済・ビジネス系メディアとしての深い知見」です。
私たちは長年、ビジネス系の雑誌や書籍を制作してきた経験から、法人のお客様、とくに経営者の方々が何を考え、どのような課題を抱えているかを深く理解しています。オウンドメディアや広報誌を制作する際には、まず企業の経営者が「何を目的とし、誰にリーチしたいのか」を最も重視します。単に面白いコンテンツを提供するだけでなく、読者が「これは自分にとって必要だ」と感じ、企業のメッセージが的確に伝わるようなコンテンツ作りを心がけています。単に多くの人に読まれることを目指すエンタメ系メディアとは異なる、ビジネスに特化したわれわれならではの強みだと自負しています。
――どのようなお客様のニーズに対して企画を提案されてきたのでしょうか。
広報誌では、金融機関、シンクタンク、メーカー、不動産企業など、幅広い業種のお客様とお取引させていただいています。
ある金融機関の会報誌では、「会員の維持」という課題がありました。そこで私たちは、会員である中小企業の経営者の方々が「この会に入っている意味がある」と感じられる内容を企画しました。具体的には、企業の法務・税務に関する最新情報を毎回アップデートできるコーナーや、会員企業の社長を丹念に取材しその奮闘ぶりを紹介する企画です。これにより、読者である経営者の方々が「自分と同じ会員がこんなに頑張っている」「このコミュニティーに属していることに誇りを感じる」といった帰属意識を高めることに成功しました。実際に、会員向けの勉強会では「読み応えがある」「毎号勉強になる」といった高い評価をいただいています。
オウンドメディアでは、メーカー、シンクタンク、リース企業、不動産会社などのお客様の支援をさせていただいております。小社の強みの1つは、「東洋経済オンライン」との連携です。あるお客様は、専門性の高い内容を発信したいというご要望をお持ちでしたが、専門性が高まるほど読まれにくくなるという課題がありました。そこで、「東洋経済オンライン」に記事を転載することで、より多くの読者にリーチし、閲覧数を増やすことができました。
別のお客様からは、「以前は自社で取材のアポイントを取ろうとしても、成功率が極めて低かったが、東洋経済と組んでからは高い確率でアポイントが取れるようになった」というお声をいただきました。東洋経済のブランドと実績が、取材先からの信頼につながっている証拠だと感じています。

――齋藤さんが考える「よいコンテンツ」とは何でしょうか?
私は「コンテンツはプレゼント」だと考えています。プレゼント選びが上手な人と下手な人がいますよね。コンテンツ作りも同じだと思っています。
よいコンテンツとは、「もらった人がどう喜ぶか、何をもらったら喜ぶか」を徹底的に考えて作られたものです。相手が喜んでくれれば、自然と贈った側もハッピーになれます。
私も過去には、「これは皆が読むべきだ」という独善的な思いで本を作ってしまい、全然売れなかったという経験があります。「求めていないもの」をプレゼントしても駄目なのです。
選ぶのに困って、安直に高価な品やブランド品、流行の品を選びたくなってしまいます。そういった品でも喜んでもらえる場合もあるかもしれませんが、そうではなく、徹底的に考えた結果、「本当に喜んでもらえる品」を考えて見つけ出すのがプロだろうと思います。
ときには、受け取り手自身が「本当のニーズ」に気づいていないこともあります。編集者やコンテンツ制作者は、読者やお客様が本当は何を望んでいるかを見つけ出す努力をして、そこをうまく捉えたコンテンツが、最高のプレゼントになるのです。
――今後、カスタム事業部で実現していきたいことは何でしょうか?
今後、カスタム事業部で注力していきたいのは、「テクノロジーの導入」です。
現在、広報物、冊子、書籍、オウンドメディアといった制作物は、アナログな手法で作られています。しかし、情報発信の未来を考えると、新たなテクノロジーの活用は不可欠です。
例えば、この10年で動画メディアは急速に成長しました。かつては何か困ったことがあれば本を読むのが当たり前でしたが、今はYouTubeで情報を得るのが一般的です。企業のブランディングや情報発信を考えるうえで、動画制作は避けて通れない領域だと認識しており、今後は積極的に取り組んでいきたいと考えています。
また、生成AIも大きな可能性を秘めています。
AIを活用することで、制作にかかる工数やコストを削減できます。これまで費用面で企業出版・カスタム出版に手が届かなかった企業様にも、AIを活用したエコノミーパッケージのような形でサービスを提供できるようになるかもしれません。制作期間の短縮も期待でき、これまで支援しきれなかった領域にも対応できるようになるでしょう。
テクノロジーを導入することで、より多くの企業様を支援できる体制を構築していきたいと考えています。
――最後に、クライアントの皆様へメッセージをお願いします。
私は30年近くビジネス書業界に身を置いていますが、この業界では昔から「よいものを作れば売れる時代は終わった」という一文が頻繁に使われてきました。これは、企業の皆様も痛感されていることと思います。今は、よい製品やサービスを作るだけでなく、それをいかに伝え、自社の商品やサービスがお客様にとってどのような価値を持つのかを発信していくことが、企業として生き残るために不可欠な時代です。
企業が税金で困れば税理士に、法律で困れば弁護士に相談するように、情報発信で悩んだ際には、情報発信の専門家にご相談いただくのが最善だと考えます。
とくに日本企業の大多数を占める中小企業の方は、大手広告代理店と継続的に付き合うことはコストの面で、すべてを自社で実施するのはリソースの面で、それぞれ現実的ではないと思います。
そのようなときにこそ、ぜひ一度、東洋経済新報社のカスタム事業部のサービスを思い出していただければ幸いです。
私たちは、長年の経験と専門知識、そして多様な人材とネットワークを生かし、貴社の情報発信を強力にサポートさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。