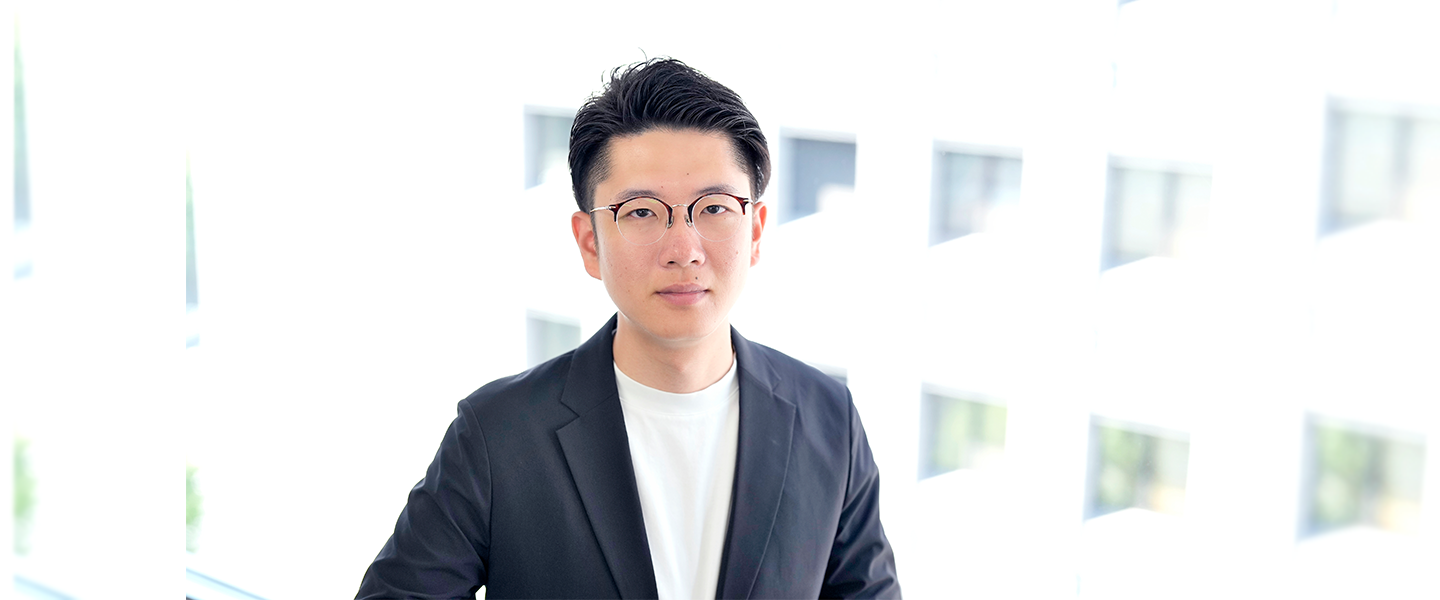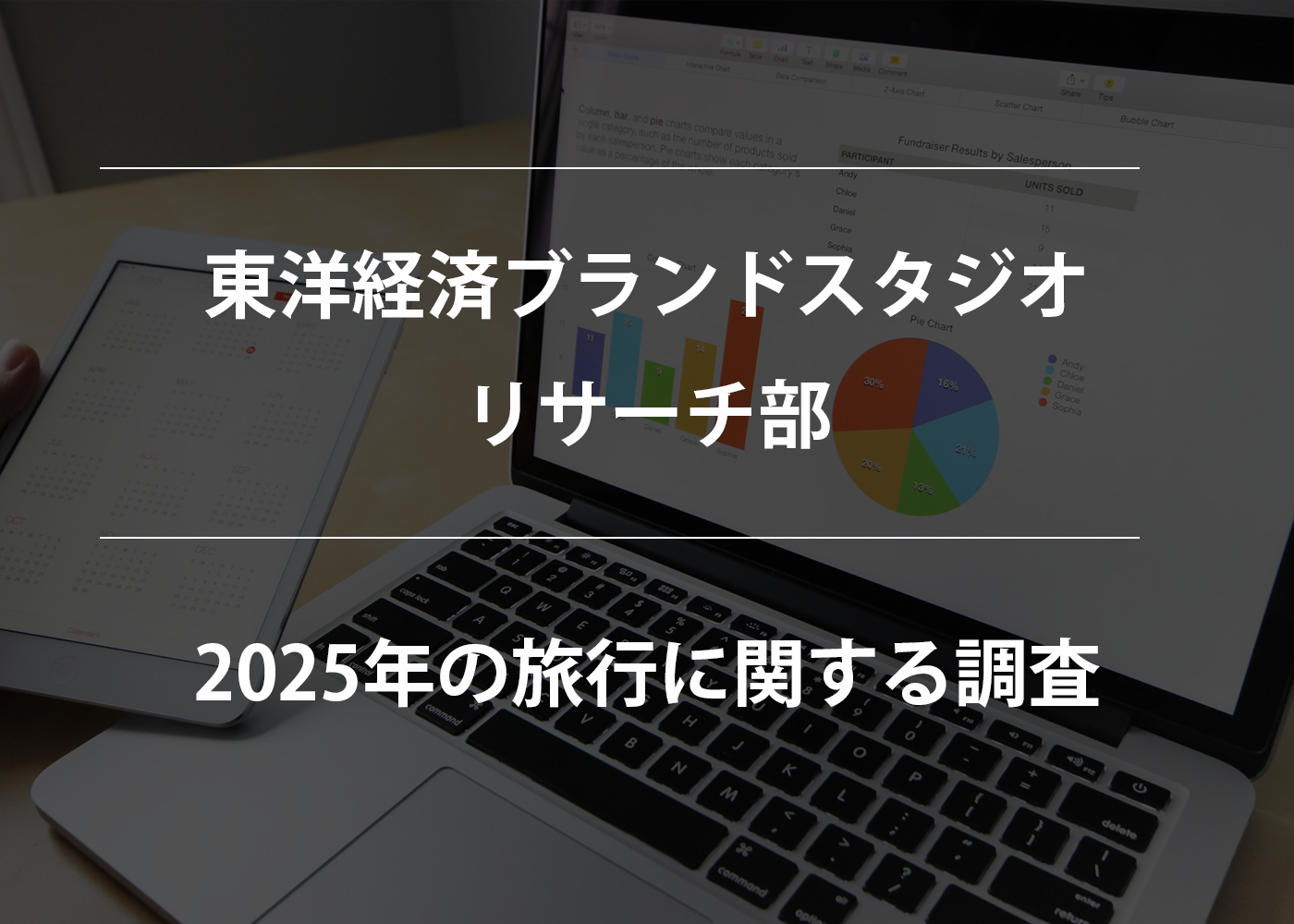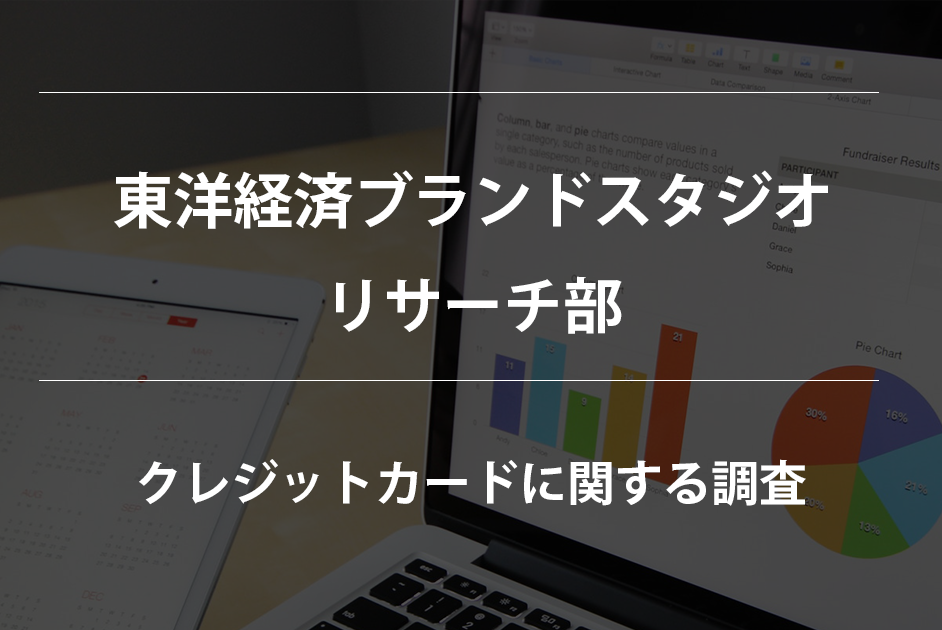協賛企業様のセミナー・フォーラム開催を支援するブランドスタジオ・セミナー事業部。
コロナ禍でしばらくの間、受講者が会場に足を運ぶ「リアルセミナー」開催は途絶えていましたが、再び協賛企業様からご相談をいただく機会が増えています。
セミナーのニーズの変化、リアルセミナーとオンラインセミナー(ウェビナー)の違いや、リアルセミナーで成功を収めるポイントについて、ビジネスプロモーション局ブランドスタジオ・セミナー事業部の宮崎大樹に話を聞きました。
コロナ禍でしばらくの間、受講者が会場に足を運ぶ「リアルセミナー」開催は途絶えていましたが、再び協賛企業様からご相談をいただく機会が増えています。
セミナーのニーズの変化、リアルセミナーとオンラインセミナー(ウェビナー)の違いや、リアルセミナーで成功を収めるポイントについて、ビジネスプロモーション局ブランドスタジオ・セミナー事業部の宮崎大樹に話を聞きました。
ーーー自己紹介をお願いします。
2022年11月に入社以来、外資系ITサービス企業様を中心に、BtoB企業様を担当しております。前職は人材サービス企業に8年半勤め、就活生向けの合同会社説明会に関する企画や運営を担当していました。
ーーー新型コロナウイルスが5類に移行し、会場に受講者をお呼びして開催するリアルセミナーの実施も増えているように感じます。協賛企業様からのセミナー開催に関するニーズの変化などがあればお聞かせください。
昨年に比べ、企業様からのお問い合わせは、リアル、またはオンラインとのハイブリッド開催のお問い合わせが増えています。
オンラインセミナーの開催はとくにコロナ禍以降急速に普及し、ノウハウが確立されました。主催者はパソコン1つで手軽に開催しやすく、参入障壁が低い。視聴者もリモートで気軽に参加できる。その手軽さから類似したセミナーが乱立して視聴者が分散してしまいました。また中には質があまり高くなかったり、主催者の製品やサービスの紹介のみにフォーカスしたものも多く、視聴者側も警戒して参加を手控えるなどの課題が浮き彫りになってきました。そういった課題を解決し、他社の主催する「セミナー」と差別化するため、リアルでのセミナー開催のご相談をいただく機会が増えています。
ただ、セミナー開催企業も受講者もオンラインに慣れておりますので、まだまだオンラインセミナーの需要も大きいです。

ーーーリアルセミナーとオンラインセミナーの違いはどういった点にあると思いますか?
例えばセミナーの開催目的が「リード獲得数」という軸であれば、オンラインセミナーのほうが向いているかと思います。PCやタブレットで手軽に受講が可能ですので、実施プログラム内でご興味のある内容だけを視聴する方や、仕事や作業をしながら受講している方もいらっしゃいます。受講ハードルがそこまで高くないので、比例してリードの獲得数も増えます。
一方で「リードの質」を重視するのであれば、リアルセミナーが適しています。日程と時間を確保したうえで会場まで足を運ぶ必要があるため、自社の課題意識が強い方、ビジネスでの情報収集への意識が高い方が集まる傾向にあります。
リアル開催ですと会場でネットワーキング(交流会)のお時間を設ける場合が多く、実際に受講者やお客様と情報交換や名刺交換などのコミュニケーションも取ることができます。
小社が企画協力という形で直近お手伝いした企業様のリアルセミナーでは、大企業の役職者の方など、ウェビナーではなかなか集客できない受講者の方が集まりました。協賛企業様の担当者からは「リアルセミナーだからこそ、普段では接点を持てない方とつながることができた」とおっしゃっていただきました。
ーーー事例についてもう少し具体的に教えてください。
小社で継続してご支援をしているBtoBの協賛企業様の事例です。2023年夏にリアルとオンラインのハイブリッドセミナーを開催しました。会場では受講者の方にお集まりいただき講演を実施し、その模様をオンラインでライブ配信するのがメインプログラムでした。
講演開始前の午前中には、協賛企業様のお得意先様や新規のお客様に対して、活用事例をご紹介したり、交流する時間を設けました。協賛企業様の営業担当の社員さんも運営として参加し、お客様をアテンドしながらコミュニケーションを取られていました。
小社も運営面でしっかりサポートをしておりますが、協賛企業様のセミナーご担当者様だけでなく、営業のご担当の方を含め一丸となって従事されていました。
協賛企業様のその情熱が、会場での「密」なコミュニケーションとなり、協賛企業様とお客様との接点創出から、製品・サービスへの関心の醸成、その先の商談化までを実現できたと考えています。

ーーー東洋経済のセミナーの特長はどのような部分だと思いますか?
まず、小社の専属ディレクターが企画から運営、その後のレポートまでワンストップで開催をお手伝いできる点があります。
東洋経済新報社開催のセミナーのパターンは「完全オーダーメイド」「複数協賛型」「集客サポート型」の3種類がございます。最もご相談が多いのが「完全オーダーメイド型」です。レギュレーションの縛りも少なく、お客様の目的・ご要望に合わせて専属ディレクターから提案を行います。
次に、集客は「東洋経済オンライン」のメールを購読されている方や、過去に弊社主催のセミナーに参加いただいた方が中心という点があります。情報感度が高く、大企業にお勤めの役職者の方にもアプローチが可能です。ご希望に合わせて属性を絞ったターゲティング集客も可能です。
またセミナーにご参加いただけなかった方に対しては、『週刊東洋経済』や「東洋経済オンライン」にてセミナーの「採録記事」を掲載することでアプローチが可能です。質の高いコンテンツをその場限りのもので終わらせず、多くの方がご覧いただける形に展開できる点を評価いただいております。
コンテンツの中身については、経済誌ならではのアプローチで、現代のビジネスパーソンが関心を持つ切り口や企画をご提案できます。また125年以上の報道・編集で培ってきた信頼と実績から、「東洋経済さんだから」ということで登壇いただける有識者の方も多くいらっしゃいます。
セミナーのリアル開催に関しては、長年のノウハウがございます。リアル開催をされたことがない協賛企業様もご安心いただければと思います。
ーーー最後にリアルのセミナーについて悩まれている方に向けてメッセージをお願いします。
リアルセミナーに対して、コストを含めて開催するハードルの高さを感じている方も多いです。まずは小規模なイベントや勉強会などでお客様とリアルにお会いし、徐々に顧客接点をつくり、そこから規模を拡大していくことがお勧めです。場数を踏むことでリアル開催に対する不安は薄れていきます。また営業担当など社内でセミナーに協力してくれる人をつくっていくことも重要です。
小社で開催をお手伝いする場合は、東洋経済の持つソリューションを駆使し、リアルセミナーの成功に向け最大限サポートいたしますので、ぜひご相談ください。
>>東洋経済セミナーの開催実績を見る
2022年11月に入社以来、外資系ITサービス企業様を中心に、BtoB企業様を担当しております。前職は人材サービス企業に8年半勤め、就活生向けの合同会社説明会に関する企画や運営を担当していました。
ーーー新型コロナウイルスが5類に移行し、会場に受講者をお呼びして開催するリアルセミナーの実施も増えているように感じます。協賛企業様からのセミナー開催に関するニーズの変化などがあればお聞かせください。
昨年に比べ、企業様からのお問い合わせは、リアル、またはオンラインとのハイブリッド開催のお問い合わせが増えています。
オンラインセミナーの開催はとくにコロナ禍以降急速に普及し、ノウハウが確立されました。主催者はパソコン1つで手軽に開催しやすく、参入障壁が低い。視聴者もリモートで気軽に参加できる。その手軽さから類似したセミナーが乱立して視聴者が分散してしまいました。また中には質があまり高くなかったり、主催者の製品やサービスの紹介のみにフォーカスしたものも多く、視聴者側も警戒して参加を手控えるなどの課題が浮き彫りになってきました。そういった課題を解決し、他社の主催する「セミナー」と差別化するため、リアルでのセミナー開催のご相談をいただく機会が増えています。
ただ、セミナー開催企業も受講者もオンラインに慣れておりますので、まだまだオンラインセミナーの需要も大きいです。

ーーーリアルセミナーとオンラインセミナーの違いはどういった点にあると思いますか?
例えばセミナーの開催目的が「リード獲得数」という軸であれば、オンラインセミナーのほうが向いているかと思います。PCやタブレットで手軽に受講が可能ですので、実施プログラム内でご興味のある内容だけを視聴する方や、仕事や作業をしながら受講している方もいらっしゃいます。受講ハードルがそこまで高くないので、比例してリードの獲得数も増えます。
一方で「リードの質」を重視するのであれば、リアルセミナーが適しています。日程と時間を確保したうえで会場まで足を運ぶ必要があるため、自社の課題意識が強い方、ビジネスでの情報収集への意識が高い方が集まる傾向にあります。
リアル開催ですと会場でネットワーキング(交流会)のお時間を設ける場合が多く、実際に受講者やお客様と情報交換や名刺交換などのコミュニケーションも取ることができます。
小社が企画協力という形で直近お手伝いした企業様のリアルセミナーでは、大企業の役職者の方など、ウェビナーではなかなか集客できない受講者の方が集まりました。協賛企業様の担当者からは「リアルセミナーだからこそ、普段では接点を持てない方とつながることができた」とおっしゃっていただきました。
ーーー事例についてもう少し具体的に教えてください。
小社で継続してご支援をしているBtoBの協賛企業様の事例です。2023年夏にリアルとオンラインのハイブリッドセミナーを開催しました。会場では受講者の方にお集まりいただき講演を実施し、その模様をオンラインでライブ配信するのがメインプログラムでした。
講演開始前の午前中には、協賛企業様のお得意先様や新規のお客様に対して、活用事例をご紹介したり、交流する時間を設けました。協賛企業様の営業担当の社員さんも運営として参加し、お客様をアテンドしながらコミュニケーションを取られていました。
小社も運営面でしっかりサポートをしておりますが、協賛企業様のセミナーご担当者様だけでなく、営業のご担当の方を含め一丸となって従事されていました。
協賛企業様のその情熱が、会場での「密」なコミュニケーションとなり、協賛企業様とお客様との接点創出から、製品・サービスへの関心の醸成、その先の商談化までを実現できたと考えています。

ーーー東洋経済のセミナーの特長はどのような部分だと思いますか?
まず、小社の専属ディレクターが企画から運営、その後のレポートまでワンストップで開催をお手伝いできる点があります。
東洋経済新報社開催のセミナーのパターンは「完全オーダーメイド」「複数協賛型」「集客サポート型」の3種類がございます。最もご相談が多いのが「完全オーダーメイド型」です。レギュレーションの縛りも少なく、お客様の目的・ご要望に合わせて専属ディレクターから提案を行います。
次に、集客は「東洋経済オンライン」のメールを購読されている方や、過去に弊社主催のセミナーに参加いただいた方が中心という点があります。情報感度が高く、大企業にお勤めの役職者の方にもアプローチが可能です。ご希望に合わせて属性を絞ったターゲティング集客も可能です。
またセミナーにご参加いただけなかった方に対しては、『週刊東洋経済』や「東洋経済オンライン」にてセミナーの「採録記事」を掲載することでアプローチが可能です。質の高いコンテンツをその場限りのもので終わらせず、多くの方がご覧いただける形に展開できる点を評価いただいております。
コンテンツの中身については、経済誌ならではのアプローチで、現代のビジネスパーソンが関心を持つ切り口や企画をご提案できます。また125年以上の報道・編集で培ってきた信頼と実績から、「東洋経済さんだから」ということで登壇いただける有識者の方も多くいらっしゃいます。
セミナーのリアル開催に関しては、長年のノウハウがございます。リアル開催をされたことがない協賛企業様もご安心いただければと思います。
ーーー最後にリアルのセミナーについて悩まれている方に向けてメッセージをお願いします。
リアルセミナーに対して、コストを含めて開催するハードルの高さを感じている方も多いです。まずは小規模なイベントや勉強会などでお客様とリアルにお会いし、徐々に顧客接点をつくり、そこから規模を拡大していくことがお勧めです。場数を踏むことでリアル開催に対する不安は薄れていきます。また営業担当など社内でセミナーに協力してくれる人をつくっていくことも重要です。
小社で開催をお手伝いする場合は、東洋経済の持つソリューションを駆使し、リアルセミナーの成功に向け最大限サポートいたしますので、ぜひご相談ください。
>>東洋経済セミナーの開催実績を見る