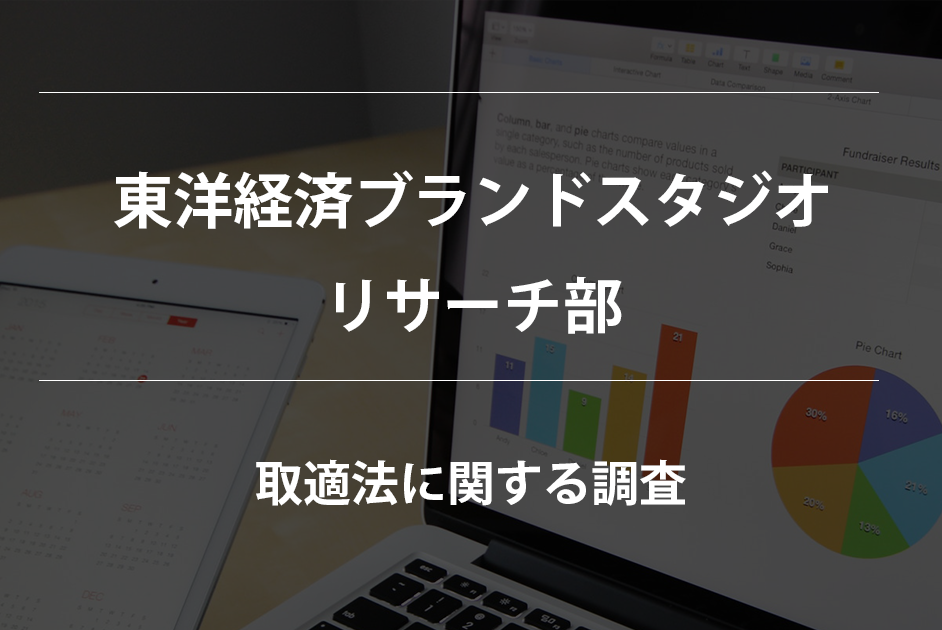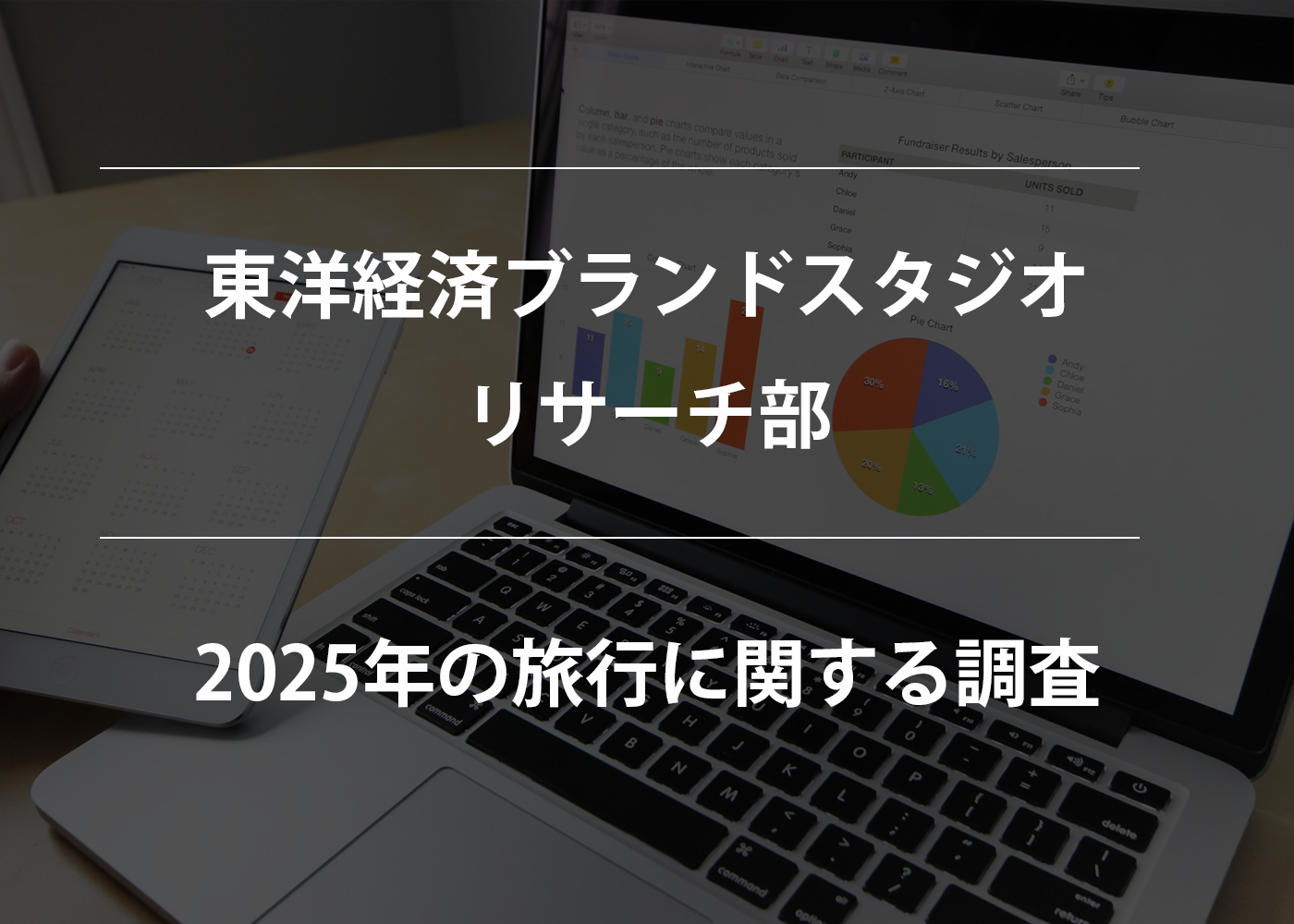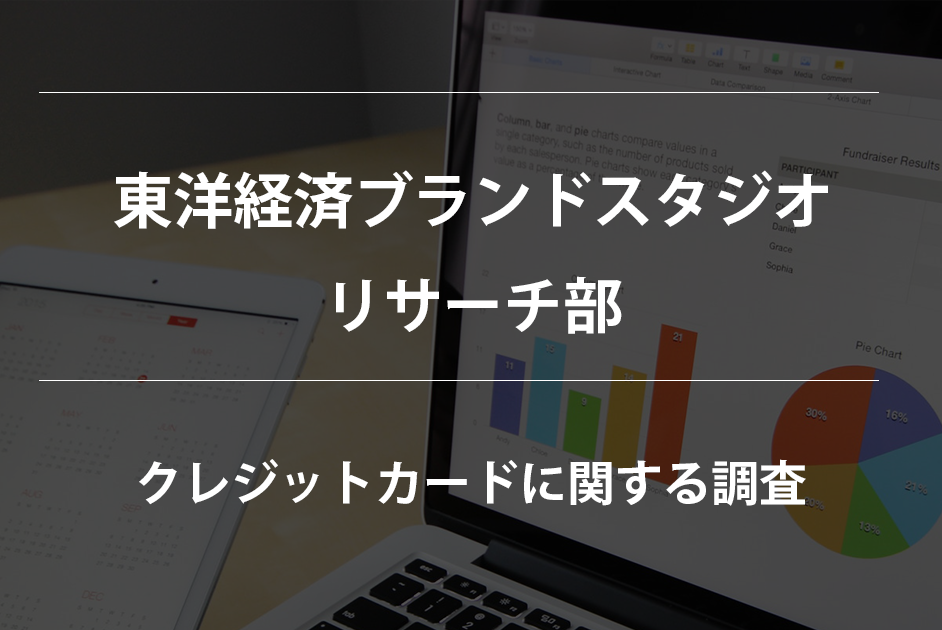SNSの急速な普及で情報の入手手段がパーソナライズ化された時代。従来のように、マスメディアから全員が同じことに関心を持つことも、同じ体験をすることもなくなった。こうした中で、企業はいったい、どのように顧客やステークホルダーとコミュニケーションをとってブランディングをするべきなのか。『ナラティブカンパニー』の著者でPRストラテジスト、本田事務所代表取締役の本田哲也氏と、ゼスプリ インターナショナル ジャパンでAPACマーケティング部長を務める猪股可奈子氏が語り合った。
(モデレーター:東洋経済オンライン編集部長 武政秀明)
「ナラティブ」とは“物語的な共創構造”である

今回のセッションテーマは「社会と顧客を捉えるブランディングとは? 社会×企業×顧客を物語で紡げ」。今、企業が発信するコミュニケーションの分野では「ナラティブ」という言葉が注目されているが、そもそも「ナラティブ」とは何なのか。日本の戦略PRの第一人者である本田哲也氏は次のように語る。
「ナラティブを辞書で引くと、物語、叙述すること、語り口と出てきます。派生語にナレーション、ナレーターがあるように、ポイントは“語り”です。私はビジネス観点でのナラティブを、その企業固有の語りから始まる“物語的な共創構造”と定義しています」
この共創構造とは、企業が単独でストーリーを発するのではなく、共に創ること。つまり、生活者、ステークホルダーと共に紡いでいくことだという。
「ただ、物語といえばストーリーではないのかという指摘もありますね。では、ナラティブとストーリーは何が違うのか。演者、舞台、時間の3つの要素に注目してみましょう。ストーリーの場合、企業を主人公とし、市場を舞台にして、起承転結で物語が完結します。一方ナラティブでは、生活者が主人公におかれ、社会全体を舞台にして、つねに現在進行形の物語が未来に続いていくのです。こうしたナラティブ的なアプローチをしている企業を、ナラティブカンパニーと呼んでいます。とはいえ、ストーリーもナラティブも、企業の強い思いが起点となる点は共通です」
「共体験・社会的距離・自分らしさ」

そう語る本田氏がナラティブカンパニーの代表格として挙げるのが、アウトドア用品メーカーのパタゴニアだ。同社のパーパス(存在意義)は、「私たちの故郷である地球を守る」。このパーパスに基づいた行動には物語性が生まれ、さまざまな人たちが巻き込まれて共創構造となるという。ほかに、味の素冷凍食品が展開する冷凍餃子のケースも挙がった。とある主婦が愚痴半分でツイートした投稿に公式アカウントで反応し、自社の「思い」と掛け合わせながらユーザーを巻き込んで情報発信を行った好事例だ。
「ちょうど、コロナ禍でエッセンシャルワーカーが注目された時期でもありました。必死に働く人の生活をサポートするという切り口のもと、冷凍食品は“手抜き”ではなく、手間を抜く “手間抜き”だという物語をSNSのユーザーと共に紡いでいき、専門家や流通をも巻き込んだ大きな現象となったのです。主婦の愚痴をみんなで“共体験”することで、単なるプロモーションではない、ナラティブなアプローチを実現させました」
本田氏は今後、企業と生活者の間には、まさにこうした共体験の向上のほか、社会的距離の見極め、そして、自分らしさ(オーセンティシティ)という3つの要素が重要になると話す。
「共体験とは、単なる共感ではなく、同じ空間で同じ課題、価値を共有すること。社会的距離とは、ブランドと消費者のエンゲージのために、企業と生活者、またリアルとバーチャルとの間に取るべき新しい間合いのことです。そしてそのうえで、各企業が持つ裏表のない自分らしさを表明し、言行一致で行動に移すこと。今後の企業コミュニケーションには以上の実践が求められます。きれい事は見透かされますから、自分たちがなぜその活動に取り組むのか、ブランドも企業もナラティブを基にしっかり意識しなければなりません」
「ヘルシーを、やみつきに。」の誕生背景

ゼスプリ インターナショナル ジャパン APACマーケティング部長の猪股可奈子氏は、先のナラティブカンパニーの概念を前提にこう話す。
「私たちも、ブランドがどんなパーパスを持ち、社会の中でどのような存在意義を確立すべきかは非常に重視しています。商品やサービスに対する共感を超えて、企業やブランドへの共感が求められる風潮は大いにありますね。一方、自社の主張を強引に押すのではなく、それを時代や消費者にどうなじませていくかは、各企業の力の見せどころだと思っています。当社は昨年から新しいタグライン、『ヘルシーを、やみつきに。』を掲げました。消費者のインサイトをより正確に理解する過程で、ヘルシーとは何かを制限して我慢するのではなく、もっと楽しんでいいものなんだというメッセージを展開したいと結論づけ、新たなブランディングにチャレンジしています」
同社のパーパスは「キウイフルーツという小さな果実の恵みを通して、世界中の人々・コミュニティ・環境の発展に大きく貢献するということ」。その背景には、株主のほとんどを占めるニュージーランドのキウイフルーツ生産者および関係者へのリターンをどう最大化させるか、そして、ビジネスの地盤となる自然とどう共存していくかというテーマがある。
これまでもさまざまな情報発信を行ってきた同社だが、実は、ブランディングの方針転換のきっかけには、とある調査の存在があったそうだ。
ブランド強化のきっかけは「とある調査」

「あるときブランドの認知調査を行うと、多くの人が、当時CMに起用していたタレントの名前しか覚えていなかったのです。肝心なキウイフルーツに関する認知がほとんど進んでいなかったことには衝撃を受けました。もちろん、タレントによる認知にも単発的な効果はありますが、ブランドの価値を中長期的に高めるためには、自分たちで何をどのように蓄積していくのかの設計が必要だと考えました。とはいえ、ただでさえフルーツ文化がない日本において、たいして心躍る見た目でもないキウイを浸透させるのはなかなか難しい。そこで、キャラクターを採用してキウイフルーツそのものを前面に押し出すと同時に、キウイフルーツの健康価値や栄養面について啓蒙的なアプローチを行い、野菜嫌いなお子さんでもおいしく楽しく栄養が取れる点などをアピールしました」(猪股氏)
こうしたメッセージが、昨今広がる「得意なものこそ伸ばす」「苦手なものはやらなくていい」という考えとも合致し、大きな注目を集めることになる。
「もちろん、注目されたからといって急速にブランド認知が進んだわけではありません。地道な取り組みを積み重ね、長期的に認知を高めてブランドを構築することが何より重要です。そのために、エージェンシーも含めてつねに消費者目線でのディスカッションを徹底しています」(猪股氏)

では、こうしたマーケティング活動において、BtoB、BtoCの違いはあるのだろうか。本田氏は、むしろ、そうした区切りでは考えないほうがいいと指摘する。
「結局、世の中というのはBtoBtoCのバリューチェーンで成り立っています。ナラティブは、そのすべてを包括して魅了できるものであるべきです」
そのうえで、猪股氏はブランディングに必要なマーケティングには2つの重要な要素があると語った。
「やはり差別性と一貫性ではないでしょうか。ほかと何が違って、どこがいいのか、それをじっくりと時間をかけて伝え続けていくことです。成果が出ないからといって、すぐに自分たちのアイデアを引っ込めるのではなく、時間をかけて育てることも大切なのです」
本田氏は、猪股氏が挙げた差別性と一貫性においても「自分らしさ」が大事になる、と説明する。
「なぜ、このブランドがこのような情報発信をするのか。今、企業やブランドにはWhyへの答えが求められています。とくにこれからのZ世代は、商品のスペックよりも企業理念への共感に購買行動が結び付くといわれています。生活者は、企業の社会における存在意義に注目しているのであり、自分らしさを欠いた取り組みはすぐに見破られてしまうのです。つまり、マーケティングの領域でも、企業広報的な姿勢が重要になってくるといえるのではないでしょうか」
世界がデジタルでつながり、社会がフラットになりはじめた現代。ストーリーでないナラティブを紡ぐためには、企業、従業員、そして生活者を含めたすべての登場人物が対等でなくてはならない。ブランドという物語を将来にわたって語り継ぐのは、企業の存在意義をつねに考え実行していく、まさに皆さん一人ひとりなのだ。