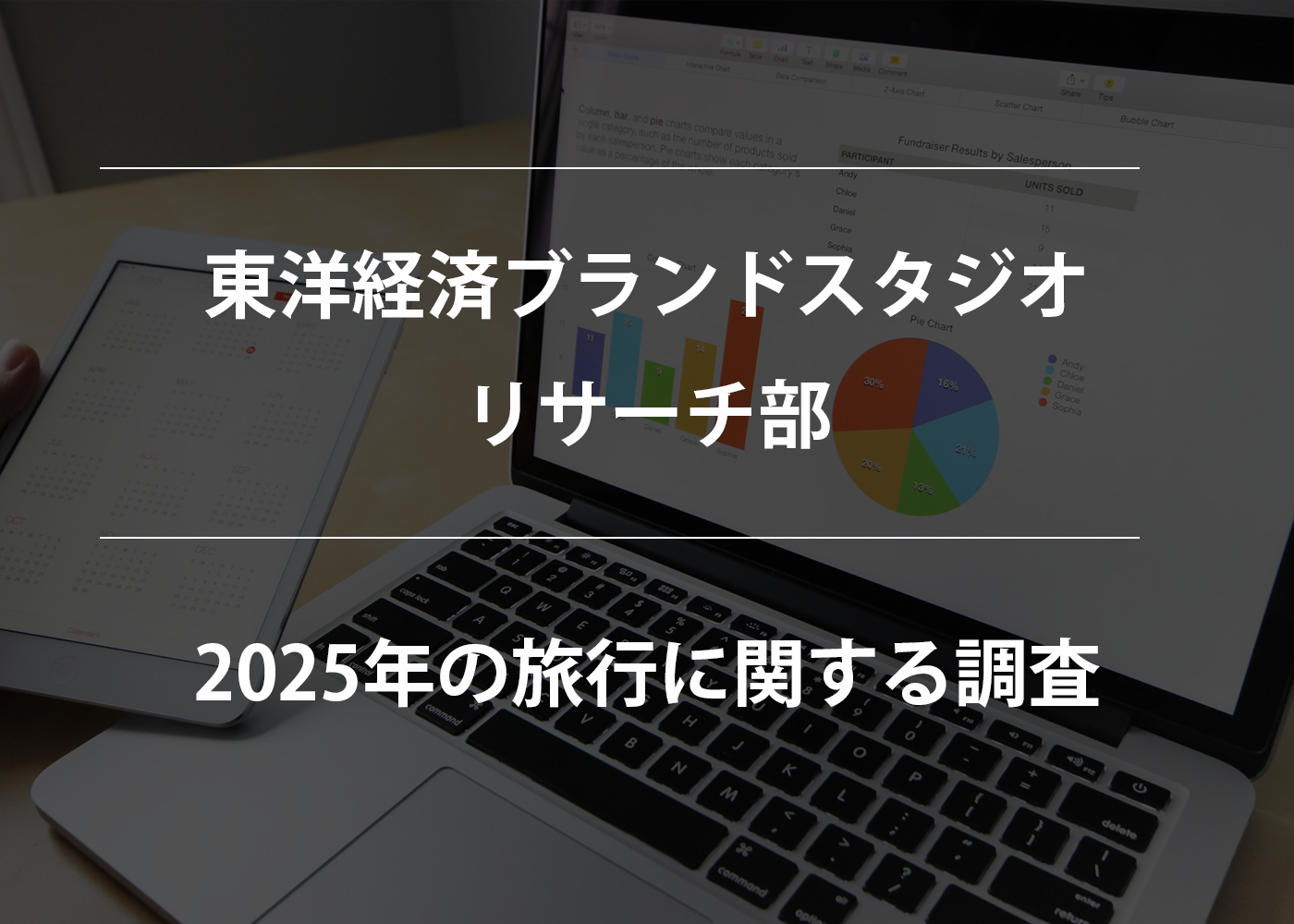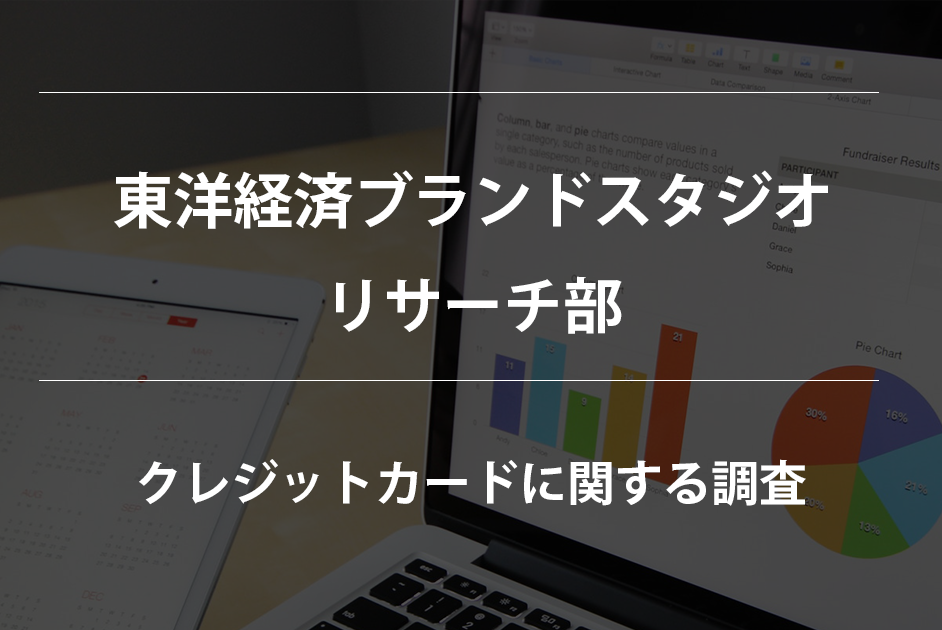2018年6月7日、赤坂インターシティコンファレンスにて、東洋経済新報社主催のマーケティング戦略セミナー「東洋経済オンラインfor BIZ」が開催されました。
セッション1は、博報堂ケトル代表取締役社長・嶋浩一郎氏と、東洋経済オンライン編集長・山田俊浩によるパネルディスカッション。嶋氏が山田編集長に質問をする形式で進行しました。
セッション1は、博報堂ケトル代表取締役社長・嶋浩一郎氏と、東洋経済オンライン編集長・山田俊浩によるパネルディスカッション。嶋氏が山田編集長に質問をする形式で進行しました。
東洋経済オンラインの現状
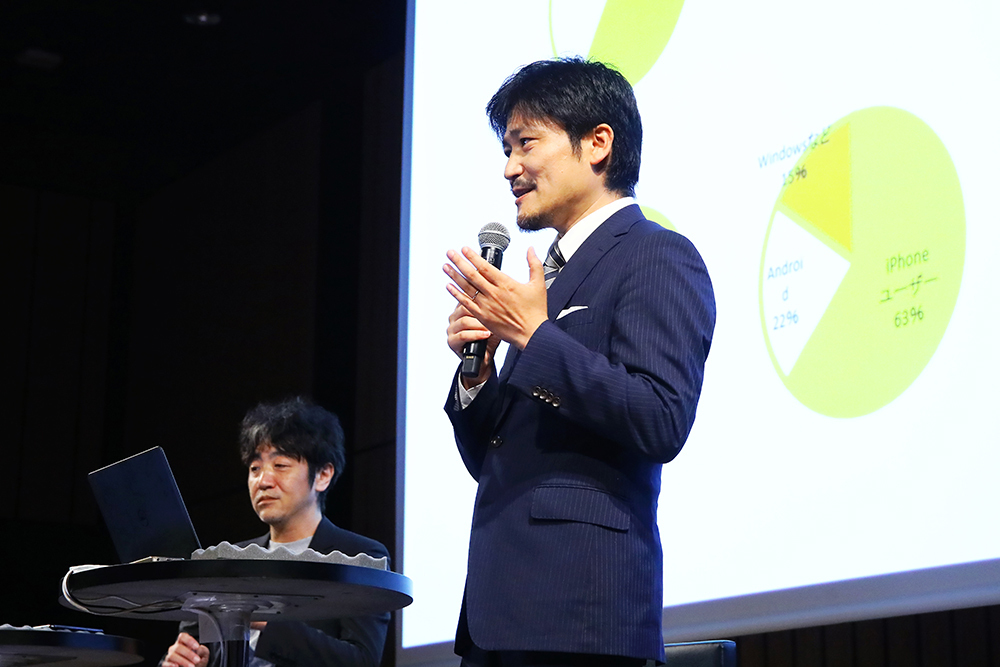
山田:現在の東洋経済オンラインのページビュー数は、月間2億前後をコンスタントに記録しています。我々は純PVと言っていますが、この2億という数は外部配信先でのページビュー数を含んでいない、純粋な東洋経済オンライン内での数になっています。
ユニークブラウザ数は、パソコンやスマホといった複数のデバイスでの閲覧を含むので高く出ます。仮に1人あたり2台の端末を使用しているとすれば、月間の閲覧人数はその半分程度です。1日あたりのユニークブラウザ数は現在平均すると120万程度ですから、毎日100万人以上の方が訪問しているということです。
閲覧者は49歳以下の方が多く、閲覧者のうち40%が女性です。
我々は他社からの転載記事を除けば、1日あたり15本程度しか記事を配信しないのですが、1本1本のページビューが多い。じっくり時間を掛けて読まれる傾向があります。
また、完全無料・ログインなしというオープンなメディアです。このスライドに示したように多くの媒体と提携しています。
中でも最近力を入れているのが、ラグジュアリ系の記事、そしてランキングのような経済ど真ん中の記事です。以上、駆け足で概要を説明しました。
編集者がPDCAを回しながら丁寧に記事を作る

嶋:2億って結構とんでもない数字だと思うんですよ。それを1日約15本という本数で実現しているのがすごい。記事もビジネスパーソンのかゆいところに手が届くような、気が利く情報に加工されている。例えば、給料の高い会社のランキングを出すんじゃなくて、給料が高くてかつ労働時間が短い会社っていうデータにしてみせてくれる。だから一本一本の記事が多くの人に読まれるんだと思うんです。2億に達するために、編集部でPDCAを回していると伺ったことがあるのですが、どのような動き方をしていらっしゃるのですか?
山田:PDCAは高速で回せば回すほどいいと言いますが、常に見ているわけにもいきません。現在は1日1回どのくらい読まれているかを示すレポートが担当編集者に送られてきます。これを見れば、どの記事が良かったか、どの記事が悪かったか、ということがすぐに分かります。またグーグル・アナリティクスのデータを元に、リアルタイムでアクセス常用をチェックするツールも用意しています。そうしたデータについては、編集部内で徹底した共有をしており、自発的によりよい記事を作っていく仕組みになっています。
嶋:東洋経済オンラインの記事は競合の経済メディアに比べてソーシャルメディアで拡散される数が多いと思うんですが、編集者は記事の拡散に対してどんな取り組みをしているんですか。
山田:TwitterとFacebookについても、各編集者が責任をもって面倒を見ています。記事編集担当とソーシャルメディア担当を切り分けてしまうと、ソーシャルメディアの中でどういう風に自分の記事が扱われているか、編集者が肌身で分からなくなってしまいます。各編集者が担当する記事は少なくていいのですが、その分丁寧に作っていき、どのように記事が流通・拡散していくか、ライフサイクルをきっちりウォッチしてもらうようにしています。
嶋:そのやり方はものすごく学びがありますよね。自分の記事がソーシャルメディアの中でどう流通・拡散しているかを毎日見ていくと、いろいろ発見があるはず。そこから記事の書き方を直していくこともできますよね。
ラグジュアリブランドと経済メディアは相性がいい

嶋:いま力を入れている領域がラグジュアリ系とランキングとおっしゃっていましたが、どういう記事がありますか?
山田:ラグジュアリについては、あまりに弱かったので少し意識的に取り組もうと動き始めた段階です。例えば、スーパーカーなど高額商品の記事はあまり読まれないんじゃないかと思っていたのですが、そんなことはなく、多くの方に読んでいただいています。
嶋:ラグジュアリブランドのクライアントさんはウエブメディアでの出稿に悩んでらっしゃると思います。ウエブでは運用型広告の出稿が一般的に行われていますが、一方で自分のブランドがどんなメディアに出ているか分からないということがある。ブランドを毀損しないメディアに出したいという需要がある時に、ブランドの世界観を保てる経済メディアであれば、ラグジュアリブランドの出稿先の一つとして可能性があると思うんですよね。
リアルイベントでの読者との対話

嶋:僕は東京の下北沢にB&Bという本屋をやっているんですが、毎日、作家や編集者を招いてイベントを開催し作家のコミュニティをつくったり、英会話やワインの教室をひらいたり、もはや本屋の業態を超えているんじゃないかと思います。
この前、東洋経済オンラインにお声がけしてもらって、書評サイト「HONZ」代表の成毛眞さん、複合型書店「Hama House」の水代優さんと一緒にいまどきの本屋のビジネスについて座談会をやらせていただきました。そこで地域コミュニティをいかに作るかみたいなお話をして、山田さんに記事にしていただきました。東洋経済オンラインのイベントは、終了後に活発な質問があったり、いいお客さんが来るんですよ。デジタル上のコンテンツとリアルな読者が集まる場がうまく機能しているなと思いました。
山田:そういうイベントを我々としても強化しています。やはり読者の方と生で会うということはとても大事です。直接意見を聞けますし、表情をみているだけでも学びがあるのです。
先週もセルジオ越後さんをお呼びして、セルジオさんのコラムと連動したトークイベントを実施しましたが、120名定員のところ1,000人以上の応募がありました。当日の出席率も高く、大変な熱気のもとで開催することができました。会場では、多くの皆さまから感謝の言葉をいただきました。
嶋:こういうリアルな読者の方を招いてのイベントもそうですし、ビジネスマンが本当に知りたいという情報を出している東洋経済オンラインは、今後とも本当に期待しています。
山田:ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。